| |
♪「序奏」<ハンドベル、ベース> 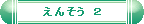 |
| 語り ・
・
|
ある夏の暑い日、リュウには、すべてがどうでもよくなっていました。 リュウは、ゆうれいのように町をさまよい、いつのまにか、町外れの森の中を歩いて
いました。
|
| 第1場 |
|
| |
鳥・風 (リコーダーとポリぶくろ) |
| リュウ ・
・
・
|
うるさい蝶だな。つきまとうな!・・・しつこいな、あっちへ行け! 行かないとたたきおとすぞ! (ばしっ・・・たたきおとす音・・・厚紙)
あ、・・・本気じゃなかったのに・・・まだ生きてる・・・
ま、蝶なんかどうでもいいか・・・どうでもいいさ。
|
| |
♪ 「どうでもいいさ」(リュウ)・・・<ピアノ、ベース、ドラムセット> どうでもいい どうでもいい どうでもいいさ いいさ
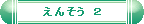
|
| リュウ |
え、どうしたんだ。うすきみわるいな・・・・・うわーっ・・・ |
| |
うす気味悪い→言魔の森へ落ちていく音楽 (シンセサイザー) ピッチコントロールなど上手に使ってました。クラスタートーンも効果的でした。
|
| 第2場 |
|
リュウ
|
「うーん、ここは・・・何がおこったんだ。・・・・・あ、きみは誰?」
|
| アムル |
「私は、あなたにたたき落とされた蝶よ。・・・もう、飛べないかもしれない。」 |
| リュウ ・
|
「ぼくはきみをたたき落とそうとしたんじゃない。うるさかったから、追いはらおうと
しただけなんだ。」
|
| アムル |
「その上、あなたにまきこまれて、ここへつれてこられたのよ」 |
| リュウ |
「え?ぼくにまきこまれたって?つれてこられたって?どういうことさ。」 |
| アムル |
「ここは、言魔の森よ」 |
| リュウ |
「え?言魔の森だって・・・」 |
| |
(言魔伯爵登場) 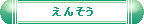 |
| |
不気味な音楽(自分で作曲) (シンセサイザー) 自分で音色をさがし、自由でふんいきのあるメロディーを作りました。
せりふにかぶせて演奏します。ブラシロールで一工夫。
|
| 伯爵 |
「その通り!・・・ようこそ、ぼうや。言魔の森へ」 |
| リュウ |
「だれだ、お前は。・・・言魔の森って何なんだよ」 |
| 伯爵 |
「私はこの森の主、言魔伯爵だ。ぼうやのリクエストでここへ連れてきてやったのだ。」 |
| リュウ ・
|
「何だって・・・ぼくはこんな所へ来たいなんて、一言も言ってないぞ! 早くもとの所に返せ!」
|
| 伯爵 ・
|
「何を言う!ぼうやは言ったではないか。どうでもいい と。(どうでもいい)
おー、なんと言う美しい言葉だ・・・。この言葉こそ、この森へのパスポートなのさ。」
|
| |
♪「どうでもいい」(言魔衆)<バス木琴、ピアノ、キーボード、ベース、ドラムセット、ティンパニ>
どうでもいい どうでもいい どうでもいいさ
どうでもよければ こわくない 気にすることなど ありゃしない
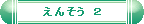
|
| 伯爵 |
「そして、この森に出口はない・・・どうでもいいんだろ。それともこわいのかい?ぼうや」 |
| リュウ |
「こわくなんかないさ。それに、ぼくはぼうやじゃない!リュウだ。」 |
| 伯爵 ・
|
「ほーっ、リュウか。いい名前だ。・・・だが、名前などどうでもいい。 おまえはそのかわいい蝶をどうでもよくたたきおとした・・・」
|
| リュウ |
「ちがう、ぼくは・・・」 |
| 伯爵 ・
|
「お前にはなかなか見所がある、いいわけなどよせ。」(いいわけなどよせ) 「だれもきかない。」(だれもきかない)「どうでもいいことさ。」(どうでもいいことさ)
|
| リュウ |
「・・・・・」 |
| 伯爵 |
「何をまよっている、そんなにもとの生活が恋しいのか?」(恋しいのか) |
| リュウ |
「恋しくなんかないさ。」 |
| 伯爵 |
「お前の本当の願いをだれか聞いてくれるか?」(きいてくれるか) |
| リュウ ・
|
「きいてなんかくれないさ。ぼくのために と やさしさのお仕着せさ。にこっとわらって
ほめられて、いい子になってりゃそれでいい。ぼくの願いなどどうでもいいのさ。」
|
| 伯爵 |
「仲間は?」(仲間は) |
| リュウ |
「自分をかくして、あたりさわりなく話を合わせるだけ。信じられるやつなんかいない」 |
| 伯爵 |
「そんな世界に何を義理立てる必要がある。・・・もう、どうでもいいんだろ」(いいんだろ) |
| リュウ |
「ああ、うんざりだ!・・・・・どうでもいいさ!」 |
| |
♪「どうでもいい」(言魔衆)<バス木琴、ピアノ、キーボード、ベース、ドラムセット、ティンパニ> どうでもいい どうでもいい どうでもいいさ いいさ
どうでもよければ なやまない 苦しむことなど ありゃしない
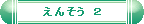
|
| 伯爵 |
「よく、言った。それでこそ、この森にふさわしい。ワッ ハッ ハッ ハッ ハッ・・・・」 |
| |
伯爵が去っていく効果音 (シンセサイザー) かみなりの音を使ってましたが、けっこうおもしろかったです。
|
| リュウ |
「消えてしまった・・・どうでもいいか。もう、つかれたよ」 |
| 第3場 |
|
| |
♪「できることなら」(アムル)・・・<ピアノ、キーボード、ベース、ドラムセット>
月の光も とどかない
小鳥の歌も きこえない
できることなら 青い空の下
かおる風の中を もう一度 飛びたい
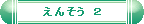
|
| アムル |
「ごめんなさい。・・・・・」 |
| リュウ |
「なぜ、あやまるんだ。・・・なぜ、そんな目でぼくを見るんだ。 ・・・なぜ、もっとせめないんだ。」
|
| アムル |
「あなたとは友達になれそうだから。・・・リュウ、あなたは感じる心を持っているわ。」 |
| リュウ |
「友達!?感じる心!?・・・・・そんなもの何になる。ぼくには、もう、どうでもいいことさ」 |
| アムル ・
|
「だけど、その心が、あなたも気づかないうちに、動き出しているの。 何か大切なものを見つけようと、もがいていて、だから苦しいの。負けないで、リュウ」
|
| リュウ |
「いまさらそんなこと・・・むださ」 |
| 第4場 |
|
| |
(伯爵登場) 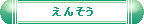 |
| 伯爵 ・
・
・
|
「ごきげんいかがかな。・・・ん!何を迷っている。・・・
そうか、その蝶の娘が良からぬことをふきこんだのだな。・・・
2度とよけいなことを言えぬよう、はねをむしりとってやる!
かまわんな、ぼうや」
|
| リュウ |
「ぼくには関係ない」(どうでもいいさ) |
| アムル |
「リュウ・・・!」 |
| 伯爵 |
「ハッ ハッ ハッ・・・ものどもその蝶をとらえよ!」(おー) |
| |
♪「どうでもいい」(言魔衆)<バス木琴、ピアノ、キーボード、ベース、ドラムセット、ティンパニ> どうでもいい どうでもいい どうでもいいさ
どうでもよければ なやまない 苦しむことなど ありゃしない
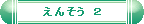
|
| 伯爵 |
「さあ、ショータイムの始まりだ。ものども、はねをむしりとるがよい。」(おー) |
| リュウ |
「まて!やめてくれ」 |
| 伯爵 ・
・
・
|
「ぼうや、何をする。気でもくるったか。
・・・名もない蝶の羽、どうなってもいいではないか。
じゃまをするんじゃない(じゃまするな)
・・・同情か、それともこの娘にたぶらかされたのか。」
|
| リュウ |
「ちがう。自分で決めたんだ。その子ともっと話がしたいんだ。」 |
| 伯爵 ・
|
「自分で決めただと・・・やめとけ、悩むだけだぞ。 どうでもいいのが一番だ。そこをどくんだ!」
|
| リュウ |
「いやだ、友達になりたいんだ。」 |
| 伯爵 ・
|
「友達だと!やめとけ、うらぎられるだけだ。 どうでもよく生きれば、苦しむことなどないのだ。」
|
| リュウ |
「・・・ぼくは、自分に素直に生きたい。・・・自分らしさを見つけたいんだ。」 |
| 伯爵 |
「な、なんてことを言うんだ!・・・・うわーーっ・・・・・・」(うわーーっ・・・) |
| |
言魔の森がくずれていく音楽 (あきカン、シンセサイザー、ドラム) あきカンを入れたふくろをゆかにおとしたり、箱に入れてふったりしてました。
シンセサイザーやドラムと合わせると、けっこう迫力がありました。
|
| 第5場 |
|
| |
鳥・風 (リコーダー、ポリぶくろ) |
| |
(リュウ目をさます。1羽の蝶がリュウのそばを飛ぶ) |
| 語り ・
・
|
リュウは、何もおぼえていませんでした。でも、何かが変わっていました。 心の中に、小さな勇気と自信がわいてきました。
そして、そばにいる一匹の蝶がとても大切に思えたのです。
|
| リュウ ・
・
・
|
もう、夕方かぁ。そろそろ帰らなきゃ。おまえも早くおかえり。 お前を見てたら、何か、気持ちが落ち着いた。・・・そうだ、名前をつけてやろう・・・
ア・ム・ル・・アムルにしよう!・・・気に入ったかい?・・・
ありがとうアムル・・・じゃあな・・・。
|
| |
♪「名前を下さい」(2部合唱)<ピアノ、キーボード、ベース、ドラムセット> 名前を下さい ひとつだけの あなたが自分で つけた名前
名前を下さい あなたらしい 夢がたくさん つまっている
もしかしたら 2度とは来ない 心ときめく 出会いの時
名前を下さい あなただけが かなえられる すてきな名前
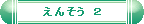
|